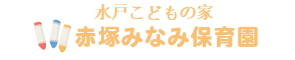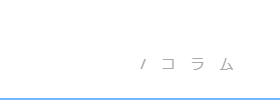2025年10月
夏の園の様子と年末にかけて
10月に入り今年の園生活も半年が過ぎ、いよいよ秋めいてまいりました。更新が滞ってしまい申し訳ありません。
9月まで猛暑といえる気候だったため、今年の夏はお外遊びやプール遊びが余り出来ずにいましたがこれからはたくさんお外で遊べますね。今年の反省としては来年からはもっと早い時期にプール開きをしようと思います。本当に長い暑さでしたね。
地球温暖化による日中の暑さ、雨が降らない日が続いたと思ったら突然のゲリラ豪雨の中を飛び交う鳥たち等を子供たちも目の当たりにしています。これはいつまで続くのかな?温暖化はどうしたら収まるのかな?エネルギーをたくさん使って便利な生活をする引き換えに二酸化炭素が排出されて地球が暑くなっていく。でも2030年頃からはミニ氷河期が来る説もあり、もしそうなったらどうなるのか等こども達とで話をしたりしました。
連日の長い暑さでいまの子ども達は環境問題が身近に感じられると思います。保育園やおうちで話し合うことで小さいころからの環境保全の意識づけをと考えています。
話が変わり、もうすぐ卒園予定の子の就学時健診があります。例年の卒園生は就学時健診で学校訪問することにより、意識が目に見えて変わってきてもっと素敵なお兄さん、お姉さんになっていきます。あたらしい事にワクワクしているドキドキしているのが手に取るようにわかるので、ワクワクにはみんなで共有をしドキドキにはそっと背中を押していきたいです。
10月はスポーツフェスティバルやクリスマス発表会の練習が始まります。年末に向けて着実に進んでいきますのでどうかよろしくお願いいたします。
保護者の皆様には何か心配事や困りごとがありましたらお気軽に連絡帳にご記入や口頭でも良いのでご相談くださいね。(和泉)
2025年6月
本年度も良好に運営されていると認められました
今年も5月に認可外保育施設の監査がありました。
毎年5月には書類を揃えての視察と監督指導があるのですが、今年も6月に良好に運営されていると認められたとの通知が届いた事をご報告いたします。
これは保育管理体制と保育内容の監査で、認められなければ保育無償化の対象施設にはなりませんので非常に重要な監査です。
これに慢心せずに通年をとおして更に尽力したいと思います。
毎年視察に来た時やお客様が来た時に、こどもたちについて「ここはとてもフレンドリーですね」と良く言われます。
子どもたちは「お客さんが来た!おもてなししたい!なにができるかな?」とワクワクするような気持ちでお迎えしていると思います。
人の為にとお客様を温かく受け入れる気持ちって大切ですよね。
そして何でも楽しいことに変えてしまうこどもたちのパワーは素晴らしいですね。
大きくなるといろいろな事にフィルターがかかり本当に大事な事が見えにくくなっていきます。
かつては家族内でも多様性が確かにありましたが、現代では核家族化がすすみ小さいコミュニティの中での価値観がそのまま自分の価値観を作っていくことが多いです。
いまの年齢では当たり前に出来ているこの事柄が、後のこころのバリアフリーにも繋がっていきます。
このまっすぐな心は大切に育てていきたいものですね。
もうすぐ7月です。暑くなってきましたので園児個々の体調等注意して過ごしていこうと思います。7月にはプール遊びも始まる予定です。元気に過ごしていきましょう。
おうちの方も、お体をご自愛くださいね。(和泉)
2025年4月
新年度になりました。
子育てについて思う事。
4月になり新たな年度が始まりました。卒園していった子どもたちも学校という新しい環境で頑張っている様子です。園のこどもたちには新しい教材も届き、みんなそれぞれ新しいワークもこなしています。保育園にも新しいお友達が増え、新しい年長さんを筆頭に輪が出来てきています。今年の年長さんは物静かなタイプですが気配り上手です。まだ慣れていない新入園児達の困ったときにすぐ気が付き、サッと行動できる素敵な力を持っています。そこに褒められたい・自分を良く見せたいなどの感情は存在しておらず本当に素敵な年長さんです。保育園の一日の生活の時間は長いので頑張りすぎないように見守っていきたいです。
4月は過去の卒園生が何人も顔を出してくれたり、電話をかけてくれました。新しい学年のスタートをきり、喜びの笑顔で私たちも嬉しくなります。何年もたっているのに、まだ忘れられていないのだなと嬉しくなります。ありがとうございます。
話が変わりますが、歳を取ってあらためて感じるのは子育ての成果はすぐではなく未来になってしまうという難しいものだという事です。そして親として子育ては無償の愛でしていても、成長によって報われる日も来るものなのだなとも感じています。世の中のご家庭には色々な方針がありますよね。褒める子育て、叱らない子育て、厳しい子育てなど家庭によって様々だと思います。これは世の他所の家庭の方針なので触れて良いものなのかと思いますが、うちは私立の保育園なので見解に触れていきたいと思いますが私は何事もバランスが大事だと考えています。
私の場合ですが普段はほのぼのとした環境になっていると思います。良い行いをしたり心の優しいところが垣間見えたり、出来なかったことが出来た時、出来なくても頑張っている時や子供なりに考え気づいた時にたくさん褒めます。数で言うと100だとします。褒めたらその分は貯金があるので躾なければいけない時(あぶないこと、人に迷惑をかける事、お友達とのトラブルなど)にその100褒めた分の範囲内で注意しているイメージだと思います。諭している間は子供に良く思われたい、嫌われたくないという気持ちはゼロでどうしてそれをしてはいけないのかをわかってもらうよう何度でも言い聞かせてきました。なぜこれをしてはいけないのかをこどもを主体として理解を深めさせることが躾で、親の都合や支配になってしまうと虐待だと考えてきました。(これが躾と虐待のラインだと考えています)
保育園の場合だと他の先生はこどもへのフォローにまわってくれています。私も他の先生もこどもへ注意をしたときは、理解がすすむとそれを応援したり理解をしたことに対して褒めており、注意しっ放しにはしていません。これが全体で自然にできているので他の先生の存在も心強く、こどもへの確かな愛を感じています。
普段、頑固なところがある子がクールダウンした後の説得ののち「わかった…。」と涙ぐんでいると、私も一緒に涙してしまうこともあります(笑)私たち保育者にもこどもの成長を支える責任があるので必死なんですよね。
普段通りの生活で以前注意されていたことが身についていた時は(うれしさもありますが)気が付くたびに成長を褒めていると思います。純粋にこの子のここが素晴らしいと思うところも素直に褒めています。それを見て周りの子どもたちの学びにもなりますし、他者への尊敬も生まれます。子どもとの間に信頼関係が出来ていれば躾の時、褒めている分もありますので注意する事も容易だと思います。親子ならなおさら容易で多少言い過ぎてしまっても普段から愛をもって接していれば大丈夫ですし、真剣な気持ちはこどもに必ず伝わります。こどもと同時に親も成長しているので、その都度アップデートしていけば良いのだと思います。
褒められることは頑張りが報われる喜びを知るために必要ですし、褒められた時の子どものちょっと嬉しそうな可愛い顔が見たいですよね。これも愛情だと思っています。
褒めるだけ、叱らない、厳しすぎる子育てに対して思うことは、こどもにとってデメリットでしかない危うい方針と思います。両親やおうちの方、もっと言えば保育園がそれぞれ主義が違うならバランスが取れる場合もありますが、どれも与えすぎるとどうなりますか?誰かが欠けてバランスが崩れたらこどもの精神はどうなりますか?で考えてみてください。バランスをとっている方が明日生きている保障もどこにもありません。保育園だと卒園してしまいます。その後の人格の形成はどうなるのでしょうか。一生こどもの人生を見守られれば良いのですが、親は順番で言えばこどもより先に死んでしまいます。その先はどうなりますか。自分が死んだ後も 一生こども自身が様々な問題を乗り越え幸福を感じながら生きていって欲しいですよね。
子育てにおいて大事な事は心を育てることで、それが本当に子供のためを思ってしている事かどうか、自分のエゴではないか、その時の子どもの気持ちはどうか理解する事でそこには愛情と尊重が不可欠です。本当の愛情は甘やかす事ではないと思っています。同時に心が傷つくほど厳しいということも心の体罰に値しその子を思っての躾ではないと思っています。
こどもたちそれぞれの個性がありこどもたちを良く見ていないと出来ない事なので、これが少人数の保育園が出来る事でその理由です。世の中には自分の子どもが他人に叱られることに対して厳しい感情を持つ方も居りますよね。保護者のかたのご理解にはいつも感謝しております。大事なお子様を預けてくださってありがとうございます。お母さんがた、今は我が子がまだ小さく、自立していくまでは目が離せず大変な時期だと思います。人間を育てるんだものそれって本当に大変な事ですよね。ですがすぐに手が離れて、いつか見守るだけでよくなる日が来ます。先を夢見て育てていきましょう。
本年度もこどもたちの成長を楽しみにしていきましょうね。(和泉)
2025年3月
もうすぐ卒園式です
今年も偕楽園の梅が綺麗に咲き誇るこの時期になりました。保育園の地域の小学校も卒業式を迎え、卒園生が顔を見せに来てくれました。キラキラと希望に溢れた喜びの顔を見られてとてもうれしく思います。あらためて保育園でその子と過ごした日々を思い出します。地域には卒園していった子が数名おり、時々顔を出してくれます。みんなのその後の成長が見られるのはとても幸せを感じますし、元気に過ごしていてくれるのが喜びです。時々、もう大きくなっちゃったから恥ずかしいという声を聞きますが、私たちの中ではいつでも大きくなってもあの時のままの「かわいい〇〇ちゃん」なのですよ。大きくなっても何があっても一緒に過ごした日々のままで気持ちが変わることはありません。だから気軽に遊びに来てくださいね。
保育園でもいよいよ月末には卒園式です。卒園式の予行練習で泣き出してしまう卒園生や在園生もおり、毎年この時期はお別れがつらいです。年長さんの新たな門出を祝い、笑顔で送り出さねばと心の引き締まる思いです。(和泉)
2025年1月
ほんとうにたいせつなこと
ほんとうに大事なことは心の豊かさと考えます。
ベースには心の安定も大事です。
わたしは豊かさの本質は物質ではなく感性(内面)だと考えています。
物事のとらえ方ひとつで、その事柄へ対する思考もポジティブに受けるか、ネガティブに考えるかが変わります。いわゆるそれがその人の価値観です。
例えば、与えられた状況に幸せを感じて生きるか、本当は幸せなのに不満を抱いて生きるのかもその子の価値観で変わります。考え方ひとつで人生において起きた苦しいこと、悲しいことなどのアクシデントも好機ととるかネガティブととるか、内面を磨いていれば大抵のことは乗り越えて強く生きて行けるのです。
子どもは親の背中を見て育つと言うように、価値観は特に小さいうちは親から子へと受け継がれていきます。子どもたちは親の考え、物事や他者に対する対応や態度を見ています。保護者の方は決してすべてが品行方正でなくても道徳心をもって行動すれば大丈夫で子どもたちはそれを見ています。
よく、子どもは放っておいてもよく育つと言いますが、子どもは育てたようにしか育たないと考えます。成長したのち良い人格を持ったのなら、それはその保護者の方が良いしつけや真面目な背中、愛情を注いでいるので良く育っているのだと思います。親が子どもに与えた環境など、子どもたちの周りを取り巻く私たちのような関わる人間も同様です。
保護者の方のしつけや道徳心、与えた環境などに倣って子どもは育っていきます。
子どもが人格を確立していく段階で保護者の方に倣った価値観は重要になります。子どもはいずれ他者の良いところ、悪いところも判断できるようになります。それを反面教師にするか否かは子供の人格による判断となります。その判断は子どもの確立していく価値観で変わるものだと思うので、小さいうちは心の教育がなによりも大事だと考えています。保護者のかたの愛情や心の教育がこどもたちの心を磨いていきます。
心の教育にはお金がかかりません。どんな家庭でも出来る教育です。人生の経験からは得ることが出来ますがお金で買えるはずもありません。多くの大人はあの時こうすればよかった、あの時の自分は思慮深くなかった、間違えていたなどと後悔を抱いたことがあると思います。それは人生の経験で学んだという事です。ポジティブな価値観や道徳的価値観を早い段階で子供が持てたなら…。とても価値があることだと思いませんか?
子育てとは心を育てることが大切だと私は考えます。
子育ては一瞬で、ある程度大きくなった段階で子どもの人格が確立してしまえば見守り助言、応援をするぐらいでほぼほぼしつけなどは終わってしまいます。子どもが自分の価値観で判断をしていくからです。子どもたちにはまだ伝わらない年齢でも、物事の本質を教えていけば気が付く日が来て、それはすべて子どもの心の糧となります。私たちのような子どもを取り巻く環境も成長段階の子どもには大事で背中を見せていかなければいけないと考えます。道徳とは心に染み込ませていくものです。まだよく伝わらない年齢でも何度でも道徳心を教えていかなければならないと思っています。
家庭でなかなか出来ないことは保育園で補えば良いと思います。保育園で、集団生活では出来ないものを保護者の方は子どもに注いでください。すべては子どもが自分の人生を幸せに生きて行く為です。
2025年も、先を見据えて行きましょう。
なにか困りごとなどを感じていましたら連絡帳に書いてくださっても良いですし気軽に園まで相談してくださいね。(和泉)
2024年 12月
クリスマス発表会と食育
12月はクリスマス発表会がありました。歌にダンスに太鼓と、発表会当日はわたし達も一緒にみなさんの演技を楽しみました。園児の皆さん、保護者の皆様も楽しい時間と感動をありがとうございました。人数の多くない保育園なので個々の演目が多く大変だったと思うのに皆さんよく頑張りましたね。
練習している間に、おうちの方や私たちに「今年は頑張る!」「恥ずかしくてできないかもしれない…。」などそれぞれ言っていたので、皆それぞれに、おうちの方と良い関係で良い環境だと思います。成長しても、その時その時の自分の困りごとを保護者の方やまわりの人達に伝える事が出来ればこれからの人生に関わる先生方やお友達もサポートができますし花丸だと思います。恥ずかしがりやさんなのは繊細で慎重であり、人の困ったことにもよく気が付ける性格の持ち主だという裏返しでもあります。それに、大人の私たちでも人前で話をしたり歌ったりは恥ずかしいものですよね。ゆっくりと慣れていきましょう。
クリスマス発表会の終わりには保護者の方扮するサンタクロースがご褒美をもって来てくださり、こども達には「もうじきたべられるぼく」という食育の絵本が贈られました。人に食べられるうしさんのお話で、うしさんが食べられるために命を捧げることを受け入れているお話です。
食育で大切なのは食事は楽しいと思うこと、いろいろなものを食べて美味しいと感じることなどもありますが、この絵本では食育のもうすこし深い道徳面をねらいとしています。決して肉食の否定ではなく食べもの全般に命があり、その命により自分の血となり肉となること、食べ物への感謝の気持ち、食べることは大きくなる為、生きるために必要な事で悪ではない事、食べることは生きるという事、命のリレーをしているのでできるだけ無駄にしない事、繋いでもらった自分の命も大事にする事を理解するのに良い絵本だと思います。
こども達によってはうしさんの抱く気持ち、やさしい気持ちにショックを受けて悲しくなったり、また現実的には思えなかったりと色々な反応がありました。年少さんには少し早いかなと思っていましたが、ふんわりと理解した感じの子が多かったので成長ののち理解を深める事でしょう。
園でも読み聞かせをしました。普段元気な男の子がしんみりして「なんか悲しいよ」といっていたり、贈られた絵本を保育園に持って来て読んでは涙を流し、お昼寝の時間には大切に枕元に置いて眠る子も居て…。こどもたちの気持ちとは、とても尊いものだなと改めて感動しました。
つばさ組さん(3,4,5歳児)のその後の給食では、残さずに頑張って食べる姿勢が見られたり気を散らさずに静かに食事をしていたり、何も言わずとも美しい所作だったりと食べるという事に対するみなさんの姿勢が変わりました。うしさんを通して命のうつくしさ、食べる事、食べることが出来る事に対する感謝の気持ちを感じているとの声も聞けて、こどもたちそれぞれの胸に響いたのだろうなと嬉しく思います。
ここから3月の卒園式までは、あっという間に過ぎることだろうと思います。
もうすぐ卒園するこどもたちとの日々をみんなで大切に過ごしていきたいと思います。
2025年も引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。(和泉)
2024年 11月
あいさつについて
あいさつは、国境や性別や年齢、また立場も越えて誰にでも話題がなくてもコミュニケーションがとれる魔法のことばだと思います。
あいさつをする相手の範囲も、声の大きさもそれぞれで恥ずかしくてできない子もいましたがコミュニケーションにより心を開いて自然と出来るようになっています。
ある朝、こどもたちの登園を待っていると駐車場から「おはようございまーす!」との声が聞こえてきました。年少さんが通りがかりの方に挨拶をしていました。それを見た時に私は嬉しい気持ちになり「元気に挨拶が出来て素敵だね。誰とでもできるなんてすごいね!先生嬉しくなっちゃった」と伝えました。その子もニコニコとした笑顔になり、見ていた私もママも嬉しいしあいさつをされた方も嬉しそうでしたし、その子のあいさつ一つで朝からみんなが幸せな気持ちになりました。年少さんだからまだ生まれて4年しか経っていないのに自分から臆せずに挨拶が出来るなんて素敵ですね。小さなころからの習慣は大人になってからも忘れないものなので社会交流の得意な素敵な大人になる事でしょうとまたわくわくするような、眩しいような気持ちになりました。あいさつを返してくれるご近所の皆様もいつも本当にありがとうございます。
今の時代、「知らない人とは話してはいけない、知っている人にも気を付けなければいけない」と教えられているので、近所の顔見知りの大人にも挨拶が出来なくなっている子供たちが一般的に多いと思います。今は高校生でも学校でのあいさつの指導があり、大人ならあいさつは大事だと誰もが知っていることなのに難しい問題となっています。「知らない人と話してはいけない」というのは危険性やその他相手の都合も考えているのだと思います。ですがその前にこども自身の「自分から誰にでも挨拶が出来る」ということが大事な事であり、挨拶をする相手なのか今は挨拶をしても良いタイミングなのかの判断は成長ののちに自ずとわかるようになります。たとえば保護者の方やわたしたちまわりの大人が積極的に挨拶をすることで挨拶をして良い範囲、しなくてもよい範囲の模範を示すことができます。危険性やあいさつとそれ以外の会話などの区別は理解が出来るようになったときに説明すれば良いと考えます。
保育園時代は保護者同伴なので安全です。理解が不確かな頃に否定されたと感じてしまうと素敵な芽を摘んでしまいます。挨拶が出来るという事は良い事なのに罪悪感をもたせたり、間違った意識を植え付けて心のバリアを作らせないように「自分から誰にでも挨拶が出来る」というその子自身の素敵な所を大事にしていきたいです。(和泉)